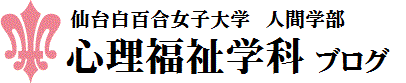白川 充
主な研究分野
ソーシャルワーク論、社会福祉教育論
研究内容
学会との関係で、このところソーシャルワーク研究法、社会福祉学研究法に関する研究に取り組んでいます。同じく学会等との関係で、生活型施設におけるソーシャルワーク実践の枠組みに関する研究に取り組んでいます。
主な研究業績
● 日本ソーシャルワーク学会監修(2020)
『ソーシャルワーカーのための研究ガイドブック』中央法規出版(分担執筆)
● 空閑浩人ほか編著(2021)
『ソーシャルワークの基盤と専門職』ミネルヴァ書房(分担執筆)
主な担当科目
ソーシャルワーク基盤と専門職(社会専門)
ソーシャルワークの基盤と専門職のあり方について、社会福祉士養成の視点から、その概要を理解することを目的とする科目です。
ソーシャルワーク臨床実習
ソーシャルワークに関してこれまで学んできた知識と技術をもとに、実践現場において、実習指導者の指導の下でソーシャルワーク実践に取り組む科目です。
増田 幹司
主な研究分野
社会政策
研究内容
社会保障と労災補償の本質に関する研究をしています。このところ十数年間は、労災補償についてユニークなシステムを採用している、歴史的に見た場合福祉国家のパイオニアであるニュージーランドの研究を主にしています。
主な研究業績
● ニュージーランド事故補償制度(通称ACC)と医療事故に関する一検討-治療行為による傷害(Treatment Injury)という概念が誕生するまでのACCの沿革-,『公共政策学』第12号・北海道大学公共政策大学院
● ニュージーランド事故補償制度(通称ACC)に関する一研究-適用範囲拡大に向けた議論と動向に関する検討-,『ニュージーランド研究』第24巻・ニュージーランド学会
●「雇用労働における今日的課題」『社会保障の保守主義(増補改訂版)』ブックウェイ
主な担当科目
社会保障論
医療保険制度、介護保険制度、公的年金制度、労働保険制度といった社会保障の各制度の仕組みを、社会保障の理念や機能の理解、さらには社会保障の構造や財源と費用等についての理解などに加えて、各制度の共通点や相違点にも着目して理解しようとすることを主眼とした科目です。
山﨑 洋史
主な研究分野
教育技法、教育臨床心理学、認知行動的セルフモニタリング、心理支援
研究内容
教育における認知行動的セルフモニタリングについて研究しています。特に、自らの持つ本来の力を十分に表現できない状態に対して、アセスメント・介入・支援していく理論・実践研究が専門です。心理カウンセリングにおける心理教育により、認知・行動の変容を協働し、新しいキャリア形成を図っていくことが研究の目的です。
主な研究業績
● 山﨑洋史、松田琴音(2021)
「心理専門家への援助要請行動を阻害する認知構造モデルの検討 -完全主義認知と恥感情に着目して-」生活心理研究所紀要 Vol.23 pp.87-102(共著)
● 山﨑洋史、吉武光世他(2017)
「新はじめて学ぶメンタルヘルスと心理学」学文社(共著)
● 山﨑洋史(2015)
「青年期食行動異常と認知行動的セルフモニタリング」学文社(単著)
● 山﨑洋史(2009)
「学校教育とカウンセリング力」学文社(単著)
● 山﨑洋史、梶田叡一他(2009)
「教育の最新事情-教員免許状更新テキスト」ミネルヴァ書房(共著)
主な担当科目
教育・学校心理学
人間の「成長・発達」を支援するために、学習・性格・適応・認知・行動・教育技法・評価・個人・集団などの教育過程の諸現象を心理学的に明らかにし、効果的な教育方法を学びます。
心理調査概論
人間の心理を科学的に理解・把握し、心理支援に生かしていくための基礎力を涵養します。ここでは、心理調査の基本的考え方と歴史、調査、観察、面接、尺度構成、検査、実践と倫理等について学びます。
渡邊 兼行
主な研究分野
記憶の認知心理学
研究内容
人間の記憶について研究しています。とくに、記憶することがらを自分で作ったり選んだりすることで、記憶に残りやすくする現象を研究しています。また、この研究の延長でひらめきが記憶に与える効果についても研究しています。
主な研究業績
● Watanabe, T. & Soraci, S. A. (2004). The self-choice effect from a multiple-cue perspective. Psychonomic Bulletin & Review, 11(1), 168-172.
● 渡邊兼行(2011)
自己選択効果研究における課題と展望 仙台白百合女子大学紀要,15,73-87.
主な担当科目
心理学概論
感覚・知覚、動機づけ・感情、記憶・学習、認知、発達、知能・性格、心理臨床、社会心理といった心理学のトピックについて概観し、心理学の全体像を学びます。
知覚・認知心理学
知的な心のはたらきを情報処理の観点から探求する認知心理学の観点から、知覚や記憶、思考などの心のはたらきを学びます。
郡山 昌明
主な研究分野
精神障害者の地域生活支援
研究内容
精神障害者の多くは、病気のことや就労のことなどさまざまな生活のしづらさを感じながら地域で生活をしています。研究の内容は、精神障害者を対象に面接を通しての支援の仕方や社会福祉制度上の問題点などを明らかにし、支援の方法を検討することです。
主な研究業績
● 利用者とソーシャルワーカーとの意思疎通を促進させる「ツール」開発の研究
● 精神障害者の就労支援における課題の明確化
主な担当科目
精神保健福祉援助技術総論
精神保健福祉士の意義や役割、歴史、価値、倫理にかかわる基礎的な事項を学びます。
精神保健福祉援助演習
精神保健福祉士が必要とする援助技術について、演習をとおして学びます。
志水 田鶴子
主な研究分野
障害者福祉分野(高次脳機能障害者の地域生活支援に関する研究)
地域福祉分野(地域住民の支えあい活動に関する研究、宮城や熊本での被災者支援従事者育成に関する研究)
研究内容
高次脳機能障害者の地域生活支援について研究をしています。またどんな状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるための地域になるように行政や専門職、地域住民とともに実践研究、実践活動をしています。具体的には生活支援コーディネーターの育成や協議体運営について研究しています。
主な研究業績
● 地域づくりハンドブック 柳史生(監修)志水 田鶴子(著)大坂純(著)
● 改正介護保険における「新しい地域支援事業」の生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)と協議体
吉田 昌司 (監修), 高橋 誠一 (編集), 志水 田鶴子 (編集), 大坂 純 (編集)
● 生活支援コーディネーター養成テキスト
高橋 誠一 (著), 大坂 純 (著), 志水 田鶴子 (著), 藤井 博志 (著), 平野 隆之 (著), 吉田 昌司 (監修)
主な担当科目
精神保健福祉援助演習
精神障害者を支援する専門職としてのコミュニケーション力や相談支援力を高めることを目的として、ケーススタディやグループディスカッション、ロールプレイなどを活用し進めていきます。
精神保健福祉援助実習
実習で出会う精神障害者から、精神障害が生活に及ぼす影響や病を抱えながら生きることなどを学び、医療機関や障害福祉サービス事業所等とそこで働く精神保健福祉士が果たすべき役割と機能等について学ぶことを目的としています。
中嶋みどり
主な研究分野
被爆者の人生における心の支え、児童虐待の認知・臨床事例に関する研究
研究内容
広島で被爆者の人生における心の支えを研究していました。最近は被爆者以外の方の心の支えを検討したいと考えています。児童福祉現場にいましたので、虐待の捉え方、心の問題をもつ子どもの事例や遊戯療法を検討したいと思っています。
主な研究業績
● ヒロシマ原爆被害者の人生を支えたもの:面接調査の発言のKJ法による分析 心理臨床学研究, 第35巻3号(2017), 256-266.
● 保護者と専門家における児童虐待の認知の特徴 発達心理学研究, 第16巻1号(2005), 72-80.
主な担当科目
心理学的支援法(講義)・心理学的支援法(演習)
心理臨床家(公認心理師・臨床心理士)が身に着ける専門的な支援法について、人と出会う根本から考え、専門的な姿勢と理論、スキルを実践的に学びます。
発達心理学
各発達段階の心の発達にみられる興味深い様相を学び、過去や未来への発達のもつ大切な意味を理解する科目です。
茂木 千明
主な研究分野
家族アセスメント
研究内容
家族心理学の立場から『健康な家族とは何か』というテーマを基に、家族の発達や変化に適応していく『家族のもつ力』について研究しています。また、家族だけにこだわらず、人間が自分らしく生きていくための身近な・大切な人やモノとの関係性にも関心があります。
主な研究業績
● 茂木千明(2015)
児童養護施設の子どもが作成した生活関係図-家族関係単純図式投影法を応用して-人間発達研究センター紀要「人間の発達」, 第10号,29-36.
● 茂木千明 (2007)
健康な家族機能に対する家族の評価 仙台白百合女子大学紀要, 第11号,65-80.
主な担当科目
コミュニケーション論
コミュニケーションの基礎や人間関係の形成について学び、対人援助に必要な人間理解の視点や援助者の心理や態度を理解します。
臨床心理学概論
臨床心理学の学習を通じて、人の心理や行動を理解する視点および援助的な関わりについて学びます。
家子 敦子
主な研究分野
在宅看護 地域健康支援
研究内容
在宅で暮らす高齢者や障害を持つ方々の生活の継続に欠かせない「医療」と「福祉」の連携に関心を寄せてきました。特に地域包括ケアシステムの社会的政策的課題において地域看護の視点は、災害や立地により行き届かない医療や福祉の一端をも担い、コミュニティの再生とかけがえのない日常を取り戻すべくその在り方を考えていく必要があると考えています。
主な研究業績
● 東北地方における急性期病院の看護師長が捉えている退院支援の構造 日本看護管理学会誌13巻2号
● 超高齢地域に暮らす高齢者が自立した在宅生活を継続するための看護職による健康支援活動 日本ルーラルナーシング学会誌第7巻
主な担当科目
人体の構造と機能及び疾病
身体構造や心身機能、ライフステージにおける心身の健康課題等を理解し、「健康」「疾病」について考え、人々の健康に影響を及ぼす要因や健康課題の解決策を学んでいきます。
レクリエーション論
レクリエーション・インストラクター養成課程の必須科目です。レクリエーションは「人生」や「生活」を豊かにします。さらに指導する立場を学ぶことによって個人の主体性や協調性、創造性を引き出す力が養われ、発展的なコミュニケーション力として身につけられることが期待できます。
高田 洋平
主な研究分野
ストリート空間に関する文化人類学的研究、滞日移住労働者の福祉的支援に関する研究
研究内容
現在でこそストリートは移動か消費の場としてその意味を切り詰められていますが、従来のストリートは、人と人とが結ぶ社会的な場でした。特に貧困層にとって重要な社会的な場としてのストリート空間について人類学的な視点からネパールを事例に研究しています。また同時に滞日移住労働者の福祉など国際福祉研究を進めています。
主な研究業績
● 高田洋平(2017)
「ストリート・チルドレンの「包摂」とローカルな実践—ネパール、カトマンドゥの事例から—」『体制転換期ネパールにおける「包摂」の諸相 言説政治・社会実践・生活世界』三元社、東京大学東洋文化研究所叢刊第31篇336-376.
● 高田洋平(2020)
「ネパールの社会福祉」『新 世界の社会福祉 第9巻南アジア』旬報社、129-159
主な担当科目
国際福祉論
グローバリゼーションに伴う新たな排除や暴力のかたちを捉える力を文化人類学の理論を用いて養うとともに、それに対して求められる福祉の在り方や実践事例を国際福祉という枠組みとして理解します。
結城 裕也
主な研究分野
感情の表出性に関わる社会心理学
研究内容
対人サービス従業者は、職務の中で自分の感情を誘発したり抑制する機会が多く、このような労働は感情労働と呼ばれています。主に、対人サービス従業者の感情労働による心身への否定的影響の緩和について研究しています。
主な研究業績
● 結城裕也、 板村英典、 安藤清志、 井上果子、 松井豊、 畑中美穂、 福岡 欣治(2009). 新聞ジャーナリストの惨事ストレス対策に対する意識 横浜国立大学教育相談・支援総合センター研究論集, 9, 79-98.
● 結城裕也、 畑中美穂、 福岡欣治、 井上果子、 板村英典、 松井豊、 安藤清志(2009). 新聞ジャーナリストにおける職務上の自己開示―職階からの検討 東洋大学大学院紀要, 46, 51-66.
主な担当科目
社会心理学
個人と個人、個人と集団、個人と社会という様々な関わりの中で、人の心の動きや行動の背景にある法則性について学びます。
心理学統計法Ⅱ
データの性質や要約に関する知識を土台とし、より高度な統計的手法を用いて人間の心を科学的に解明する手法を学びます。
吉田 弘美
主な研究分野
介護福祉学、福祉専門職養成教育、介護技術(福祉用具活用法)など
研究内容
障害や加齢など介護を必要とする生活施設での経験を踏まえて、教育・研究の世界に入ってきました。福祉サービス利用者の尊厳ある生活を支えるための課題解決に向け、質の高い福祉人材として期待される学生や福祉専門職を対象に、実践現場と連携を図りながら研究を進めています。
主な研究業績
●「東日本大震災における支援物資としての介護機器の支援状況に関する検証研究」(共)第23回フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団報告書2013
●「環境因子からみた介護福祉士養成の現状」(単)仙台白百合女子大学紀要第21号、2017
主な担当科目
障害者福祉
障害をかかえる人が活用できる制度を中心に、社会の中で豊かなに生きるための支援のあり方など障害者福祉に関する知識を学びます。
社会福祉援助技術演習Ⅰ
社会福祉相談援助の基本となるコミュニケーション技術や事例を通しての利用者理解、ソーシャルワーク展開過程など実践的に学びます。
三浦 和夫
主な研究分野
認知症ケア、家族介護者支援、介護離職
研究内容
現在は、認知症高齢者を介護する家族介護者の支援に関する研究や介護職員の離職軽減に関する研究を行っています。
主な研究業績
● 三浦和夫・加藤伸司(2009)
「認知症の行動・心理症状に対する介護職員のとらえ方と研修との関係について ―在職年数別にみる内部研修の有効性―」『日本認知症ケア学会誌』8(1),51-59.
● 三浦和夫(2014)
「通所介護職員における職場特性に関する研究 ―性別・雇用形態別の比較検討―」『社会福祉学』55(1),88-89.
主な担当科目
介護福祉概論Ⅰ・Ⅱ
介護福祉概論Ⅰ・Ⅱでは、主に高齢者の特性、高齢者福祉の歴史、介護保険制度などについて学びます。
介護実習
介護実習では、担当利用者を1名受け持ち、介護過程を展開します。また、生活を支援するための技術も学びます。