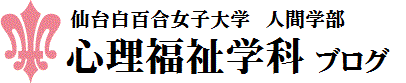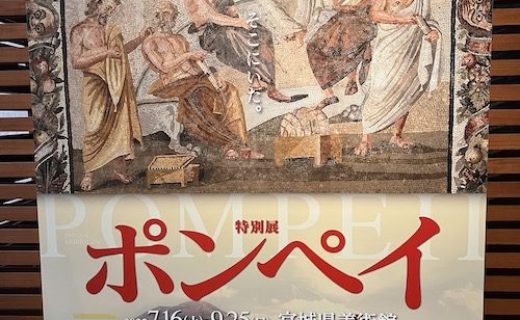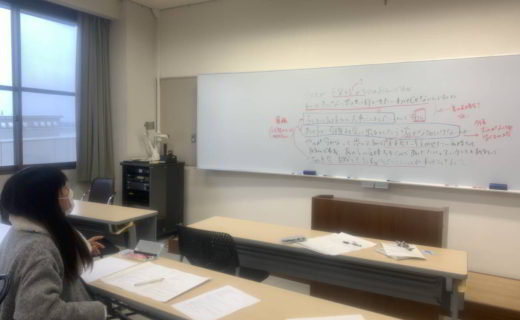こんにちは、教員の高田です。
心理福祉学科は心理と福祉を基礎にしながらグローバルなセンスも磨くことができる珍しい学科です。グローバルなセンスとは簡単にいえば、異文化を理解する力のことです。
これは特に福祉の現場でも「文化的能力」ということで近年、日本、そして世界のソーシャルワーク実践の現場で重要視されています。それはおそらく心理も同じなのか、カウンセリングの対象として外国人の子どもが増えてきているといった話も聞きました。
いずれにせよ在日外国人が急増する日本において、このセンスは間違いなく色々な場面で役に立ってくるでしょう。少しでも関心があればぜひ、ともに「異文化とは何か」「異文化を理解するとはどういうことか」を学びましょう。そして何より「外国籍の方と異文化に触れ、それを理解することがこんなにも楽しいものなのだ」ということを、入学後に経験してもらえたら嬉しいです。
さて前記事でもお伝えしたように、今私は、南アジアの国、ネパールで調査をしています。まさに異文化のなかにいるわけですが、今回もその一場面を紹介。
ネパールの首都、カトマンドゥの道を歩いているとふとしたタイミングで古代、中世の寺院が目の前に現れることがあります。今回もフィールドワーク(調査)中に、写真の寺院にいきあたり、そこで柔和な顔をしたブッダの彫像に出会いました。

頭のうえに置かれている花は、日々の儀礼(プジャ)で供えられたものです。構図も少し日本の仏像とは違いますね。また石で制作された仏像というのも日本ではあまりみない気がします。この石仏の制作時期は12世紀から18世紀のマッラ王朝時代と思われますが、高度な石の彫刻技術で栄えた4世紀から7世紀のリッチャビ王朝時代の可能性もあり、想像が膨らみます。
実はこの日の朝、ホテルからみえた朝陽が素晴らしくて「よし、40代はブッダのいう三毒(貪り、怒り、無知)を抑えた時間を過ごそう」と決意しました。ご存知の方もおられるかもしれませんが、ブッダは人間を堕落させるものとして三毒を唱え、それを抑えることを示されました。私は禅仏教とキリスト教に縁を頂いてきたものの敬虔な仏教徒ではありません。しかし三毒は頭に残っていて、ふとそのように思い立ちました。こう考えたのは最近、怒りっぽい自分がいるからです。あまり怒りたくないなあと少し悩んでいたところ、朝日のきれいさに胸をうたれ、我が身を蝕む「怒り」、ついでに他の二毒を抑えるという決意をしたのです。そういった経緯があったのでなんとなくこの彫像との出会いが嬉しくて、自然に合掌していました。
しかし・・
その数時間後、お昼に立ち寄った散髪屋でインド人とこんなやりとりをしました。
(散髪後)
インド国籍の方「1500円です」
私「え?あなた!300円ポッキリって言ったよね!」
インド国籍の方「それはヘアカットだけだ!」「あなたは髭剃りもスキンケアもマッサージも受けたでしょう!!(怒)」
私「それなら値段最初に言ってよ!おかしいでしょう(怒)」
インド国籍の方「ここに書いてあるでしょう。メニュー、みて」
私「いやおかしいよ(怒怒)。警察呼びますよ。とにかく私は800円しか払わんぞ(怒怒怒)」
インド国籍の方「ちっ(800円でも高いのでまあいいか)」

はい笑 「40代は三毒を抑えて生きるのだ」と朝日に決意したその日の昼に、インド人と散髪代500円をめぐって喧嘩するという。笑 人の業ってこんなに深いものですかね★
でもまあこれも異文化接触のひとつですね。システムの違い、お互いに外国人同士であることから、ときにヒリヒリすることもあります笑(が、実際はそう滅多にありません。こんな場面は私も20年ぶりでした)。しかも、うえで「インド国籍」と一括りにしていますけれども、全員がそうではないしそれは我々日本人についても言えることですしね。
まあそんなこんなで異文化のなかにいると色々なことが起こりますが、それらを含めて一緒に心理と福祉という確固たる専門を基礎にしながらグローバルなことも「楽しい」と思える知性と教養を本学科で身につけることができたら嬉しいです。
ところで。こんなとき、つまりどうしようもない自分に直面したときに、できることはなんでしょうか。私見では、諦めてありのままの自分を受け入れ、認め、決意すること。それを的確に表現した文章を私の大好きな小説から以下、紹介して終わります!
「今ここにある己を引きづって、生涯をまっとうせねばならぬ。その事実に目をつぶってはならぬ。私は断固として目をつぶらぬ所存である。でも、いささか、みるに耐えない」。
(森見登美彦『四畳半神話体系』角川文庫より)
「でも、いささか、みるに耐えない」が最高にいいですよね笑
以上、お疲れ様です!