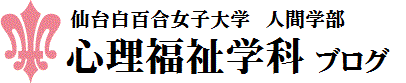韓国フィールドワーク3日目!!
本日のテーマは高齢者!!今回の韓国フィールドワークのテーマは「自死率の高さからみる韓国社会」ですが、高齢者は自死と関係ないのでは?
いえいえ。実は韓国では高齢者の自死率がとても高いんですね。若者がプレッシャーで、就職難で、というのは想像に難くない部分があるのですが高齢者が自死してしまう、というのは日本ではあまり聞きません。
自死、特に韓国において高齢者が自死してしまうのはなぜか。この辺りについて調査を行うために本日は二箇所、施設・機関を訪問しました。
一つ目は「ソウル市北区高齢者保護センター」です。ご対応くださったのはいずれもソーシャルワーカーのキム先生と所長のピョン氏。



ここでは主に「高齢者虐待防止」に関するさまざまな取り組みが行われていてそれについての説明を受けました。
そう。高齢者虐待、というのが実は韓国社会では高齢者の自死の一つの背景になっており、近年、増加傾向にあるのだそうです。
興味深かかったのは、ここでも経済的な要因と世代間の価値観の違いが虐待の背景になっているということでした。韓国社会において親は子どもを育てるために子どもにすべての財産を注ぎ、老後もともに暮らすなどして自身のケアを子どもに委ねるという規範が存在していたそうです。しかし近年、その伝統的価値規範が揺らぎ、そもそも親のケアを規範とみなす子どもが少なくなった。そこに加えて厳しい経済状況で子ども世代には親のケアをするゆとりがない。その結果、高齢の親は期待したケアを受けられないだけでなく、子どもにとっては経済的な負担をもたらす存在とみなされてしまう、という話でした。
そうして起こる高齢者虐待の特異な事例としては、外国旅行時に家族によってその国に置き去りにされてしまった高齢者の話がありました。
さらに韓国は社会保障制度が十分ではなく、高齢者虐待についてもカバーできる範囲が限られていることなど、韓国社会の社会保障制度の課題についても理解を深めました。
こういうやりとりをしているとふいに「日本はどうか」と思考がうつることがありますね。学生もきっと日本はどうだろう、という視点で改めて考える場面もあったかと思います。これこそが海外フィールドワークの良さのひとつ。他国の現状をみて自身の足元が見えてくるといったことがあります。学生にとって学びが大きいといいなと思います。


午後はソウル市で、すなわち韓国でもっとも大きな高齢者養護施設・機関である「ソウル市ドンブ高齢者ケアセンター」を訪問しました。カトリックの精神に基づく団体でHuman福祉会という法人が設立した施設です。
デイケア、リハビリ、特別養護老人ホーム、看護医療サービスなど複合的なサービスを展開しており、300名の入居待ちの方がいるなど非常に大規模な施設でした。ここでも尿漏れをAIで判定、通知がいくシステムなど先進的な実践について紹介を受けました。
韓国の高齢者の自死の背景の一つには高齢者向けの社会保障・福祉サービスが十分ではないということは事前学習で学んでいましたがそうした状況下にあってもこうした韓国国内の先進的な取り組みが結果的に自死を減らすことにつながっている可能性について理解することができたように思います。



研修は15時には終わりました。本日は早めのホテル着になりそう!疲れも溜まっていたのでよかったよかった。と思ってバスでホテル近くまでいったときにハプニング発生!!!!
ドライバーさんに前の訪問先から電話が入り「忘れ物がある。手帳に、フィールドノート資料・・」とのこと。だれやねーーーん!!!!!ってすぐに判明。
はい、私(教員)です・・・。結局、バスは施設まで引き返し。そして逆方向のちょっとした渋滞に巻き込まれ、ホテル着はいつも通り17時近くに・・・。
これは流石の私も「だるっ・・」って言葉が自分自身に出てしまいました。でもね、先生は思います。人がこういうミスをしたときに、学生はもう少し暖かい眼をした方がいいんじゃないかなって★

夜はまた一人で飯屋探すか!と思っていましたが、フィールドワークに参加していたゼミ生二名(2年生)とたまたま語学研修で韓国に滞在していたゼミ生(4年生)と食事をすることにしました。これがもう面白くていい時間でした。
冒頭、2年生へのメッセージを促された4年生から2年生に向けてでた言葉は「(高田)先生を信じ切ってはいけない!」ということでした。
「うんうん!^^、え!?」みたいな感じになる私。しかしその後、「うんうん!その通り」と伝えました。
4年生の言葉の主旨は、「ゼミは自分たち学生が作り上げていくもの」「先生のお膳立てを期待してはいけない」ということです。そうそう、よく理解してくれたと思いました。ゼミは学生が主体です。こちらがお膳立てしすぎてはいけない、と常日頃から思っています。社会に出ると誰かが自分のお膳立てしてくれていることなどほとんどありません。むしろ自分で手探りで進み、考え、また手探りで進まねばいけない場面の連続。
そうした力は教員がお膳立てしすぎると身につかない、そんなふうに思います。だからこそ学生は他人や教員、環境ではなくまずは自力を本願として、自分自身を信じなければいけない。
この4年生はそうしたことをわかりやすく伝えてくれたと思いました。ちなみに「先生を(全てお膳立てしてくれると)信じ切ってはいけない!」という言葉に対して2年生はなんと答えたか。「はい、それはわかっています!」
なかなか鋭い学生です。笑 率直なやりとりって面白いですね。関西生活が長かった私は裏表の少ない、率直なやりとりのなかに身を置くと気が楽になります。
初の引率仕事でそれなりに疲れていた私にとってこの時間は、一服の清涼剤となりました。以上、お疲れ様です!!