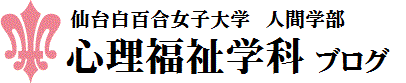2月9日(土)、社会福祉援助実習の報告会を開催しました。
2月9日(土)、社会福祉援助実習の報告会を開催しました。
実習は、医療機関や障害者福祉サービス事業所で180時間行います。
学生は、2年生の後期から少しずつ実習先について調べます。担当教員とどのような実習をしたいのか、将来どのような分野で働きたいのか、どのようにして学ぶのかなど話しをしていきます。春休み前に具体の実習先が決まります。3年生の4月からこれまで話し合ってきた実習内容について”実習計画書”で明文化していきます。実習計画書は、何回も教員の添削を受けながら作成していきます。実習は、いわゆる3層構造で進められていきます。それは、“職場の理解”、“職種の理解”、そして“ソーシャルワーク”です。
現場で働く為には、自分が所属する機関を理解しておかなくてはなりません。理念は何か、何に貢献するのか、どのような職種と連携をとるのか、そして、支援するための視点や考え方、法・制度、具体の援助技術などなど理解し身につけなければなりません。
作成した計画書に現実味があるか、場合によっては、計画の内容を変更することもあります。実習前には、実習前訪問ということで実習先に赴き、学生自身が立てた計画が実行できるかを実習指導者に確認してきます。より現実味が増すように指導を受けます。
臨床実習では、患者の退院支援、障害者の就労支援、地域活動支援など座学で学んできたことを臨床の場で考えたり、体験したりします。
報告会では、多職種連携とは何か、社会福祉士とはどのような存在なのか、ソーシャルワークとは何か、ストレングス視点の重要性、レジリエンスとはどのようなことなのか、介護保険制度の具体の内容、成年後見制度、病者ではなく生活者としての視点とは何かなどなど、たくさんの学びを報告します。
報告会には実習指導者の方、将来社会福祉士を目指す下級生が参加をし、3年生の発表を真剣に聞いています。発表が終わると、担当した指導者の方から質問や評価のコメントをいただきます。その受け応えも学びになります。学生は、再度自分自身の学びを整理していきます。
このような経験を踏まえて、2年後臨床の場に向かうことになるのです。